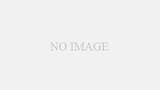「うちの子、もしかして発達に特徴があるのかな?」と気になったことはありませんか?また、周囲から指摘されて戸惑っている親御さんもいらっしゃるかもしれません。
発達のことを考えるのは、決して悪いことではありません。お子さんがより快適に生活できる方法を見つけるための第一歩です。このページでは、神経発達症(発達障害)の診断方法や流れについて、分かりやすくお伝えしていきます。
発達のことを考えるのは、決して悪いことではありません。お子さんがより快適に生活できる方法を見つけるための第一歩です。このページでは、神経発達症(発達障害)の診断方法や流れについて、分かりやすくお伝えしていきます。
神経発達症(発達障害)とは?診断基準について
神経発達症(発達障害)は、お子さんの脳の発達の特性によって、日常生活やコミュニケーションに影響が出る状態のことを指します。代表的なものに以下のようなタイプがあります。
-
自閉スペクトラム症(ASD):対人関係が苦手だったり、こだわりが強かったりする傾向。
-
注意欠如・多動症(ADHD):集中が続きにくい、じっとしているのが苦手。
-
学習障害(LD):読む・書く・計算することが難しい。
診断は、国際的な診断基準(DSM-5やICD-11)をもとに専門医が行います。ですが、大事なのは診断名よりも、お子さんがより良い環境で過ごせるようにすることです。
発達の診断方法について
発達の診断には、いくつかの検査を組み合わせて行います。当院では、別の発達診断を行なっていますが、ここでは一般的な発達の診断方法をお伝えします。
1. 発達検査
お子さんの発達のバランスを見る検査です。
例えばADHDや自閉症、感覚特性の質問紙などがあります。
例えばADHDや自閉症、感覚特性の質問紙などがあります。
2. 知能検査(IQテスト)
お子さんの知能の特性を知るために行います。
- 新版K式発達検査:知能や言葉、運動能力を評価。
-
田中ビネー知能検査:知的発達の確認に使用。
-
WISC-IV / WISC-V(6歳以上向け):ウェクスラー式知能検査の一種で、知能のバランスを詳しく評価。
-
WPPSI(ウィプシー)(幼児向け):ウェクスラー式知能検査の幼児版。
3. 行動評価尺度
お子さんの行動の特徴を保護者や先生の観察をもとに評価します。行動評価尺度は、問診や診察だけでは分かりにくい日常の様子を客観的に把握するのに役立ちます。
具体的には、保護者や学校の先生にアンケート形式の質問票を記入してもらい、お子さんの行動の傾向を数値化して分析します。これにより、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの可能性を探る手がかりになります。
-
CARS(自閉症行動評価尺度):自閉症スペクトラム症の特性を評価するためのチェックリスト。
-
Conners3(ADHD評価尺度):ADHDの症状や特性を評価するための尺度。
これらを総合的に活用し、お子さんの特性に合った支援を考えていきます。
診断までの流れ
まず一番初めに、お伝えしておきたいことは、初診の当日に診断名がついて、お薬が始まることはまずないということです。
特にお子さんの場合、初診の時には緊張してうまく医療者と関係を築くことができないことも多いため、複数日に分けて診断のプロセスが実施されるのが一般的です。
1. 問診・診察
お子さんの発達に関する気になることを詳しく伺います。多くの場合「問診票」への 記入によってなされることが多いです。
かなり細かい質問が並んでいますので事前に準備しておくことが大切です。受診前に問診票が手に入る場合が多いので、これまでのお子さんの成長を振り返ってゆっくり記入しておくのもおすすめです。
2. 発達検査・知能検査
必要に応じて、発達検査や知能検査を受けます。
3. 診断と説明
問診・診察と検査データを総合的に判断し、診断名を説明します。検査の結果、診断基準に当てはまらない場合は「グレーゾーン」と言われることもあります。
また、検査データをもとに、お子さんの苦手な部分や困りごとについて解説し、対応策を検討していきます。必要な場合はお薬の治療が提案されることもありますが、多くの場合は環境調整や教育・福祉的な支援策を提案されます。
特にお薬の治療が必要ない場合は、診断を経て診察が終了することもあります。
相談前にやっておくと良いこと
せっかくの診察時間を有効に使うためにも、事前に準備しておくと安心です。
1. 子どもの行動や特徴を観察して記録する
日々のお子さんの行動を観察し、メモに残しておくと診察時に役立ちます。
2. 家族や周囲の意見を聞く
保育園や学校の先生の意見を聞いておくと、診断時の情報提供に役立ちます。
3. 過去の記録を整理する
母子手帳や学校の通知表、連絡帳などを確認し、必要な情報を整理しておきましょう。
4. 相談先を確認し、早めに予約を取る
発達外来や専門機関は予約が必要な場合が多いため、早めに問い合わせると安心です。
当院の「ママカルテ」の特徴
「診断名が知りたい」という親御さんもいますが、多くの親御さんが本当に知りたいのは、「わが子をどう成長させるか」という具体的な方法です。
診断後、お薬の治療が必要ない場合は診察が終了することもあり、日常の困り事を解決する対応策が分からず悩まれる親御さんが多いのが現状です。
そこで当院では、診断名をつけることを目的とする上記のような診断ではなく、お子さんの日常の状態を知り対応策を見つけることが目的の当院独自のの発達診断「ママカルテ」を実施しています。
診断をすると、お子さんの現在の課題が明確になります。その中でも、特に本人の生きづらさや親御さんのしんどさにつながっている根本部分を解決することを大切にしています。
お子さんの課題が多いと、親御さんは「全部の課題を解決しなきゃ!」と頑張りすぎてしまい、行き詰まってしまうこともあるため、課題を整理し、今やるべきことにフォーカスして、親御さんもお子さんも無理なく、楽しく成長できる具体策をお伝えしています。
ママカルテで得られるもの ① 親子の「今」を知る発達診断
ママカルテでは、まずお子さんと親御さんの「今」を知るための発達診断を行います。
実際に医療機関・教育機関・児童相談所や保健所などの行政機関で使われている心理検査や質問紙を用いて回答していただき、 お子さんや親御さんについて、現時点での課題と、これから伸ばしていける強みをお伝えします。
実際の結果報告レポートでは、各項目のアセスメントを詳しくご報告し、レポートはメールでお送りします。 このレポートを参考に、園や学校の先生と支援について相談することも可能です。
ママカルテで得られるもの ② 薬に頼らず、親子の未来を創るフィードバッグ面談
診断の結果を解説するフィードバック面談をオンラインで実施しています。
一般的な医学診断では、「診断がつきました。では、こういうところに気をつけながら様子を見ましょう」ということが多いですが、 当院の「ママカルテ」では、「様子を見ましょう」とは言いません。
お子さんと親御さんの課題を解決するために、おうちでできる具体的なサポートプランをご提案します。